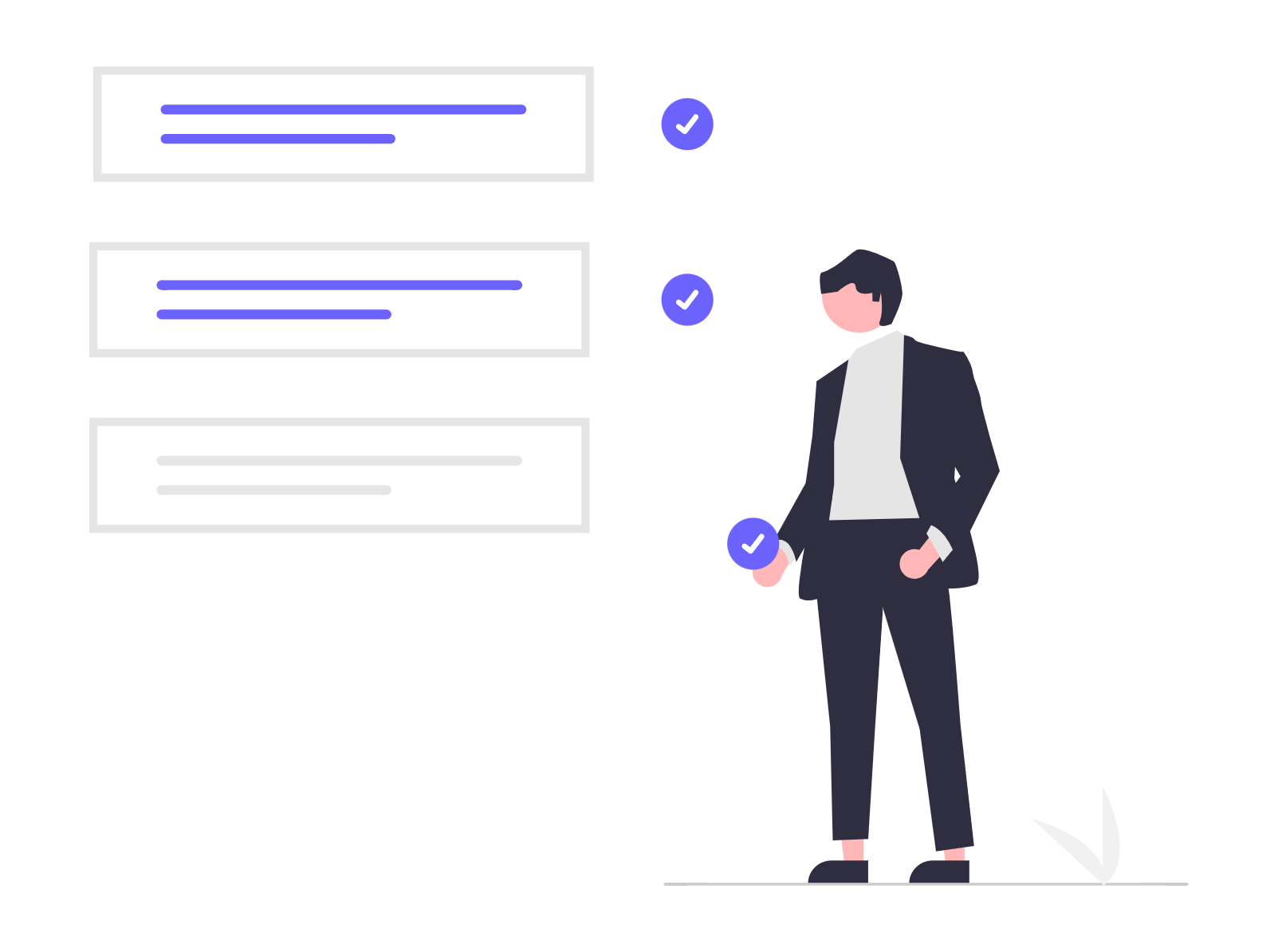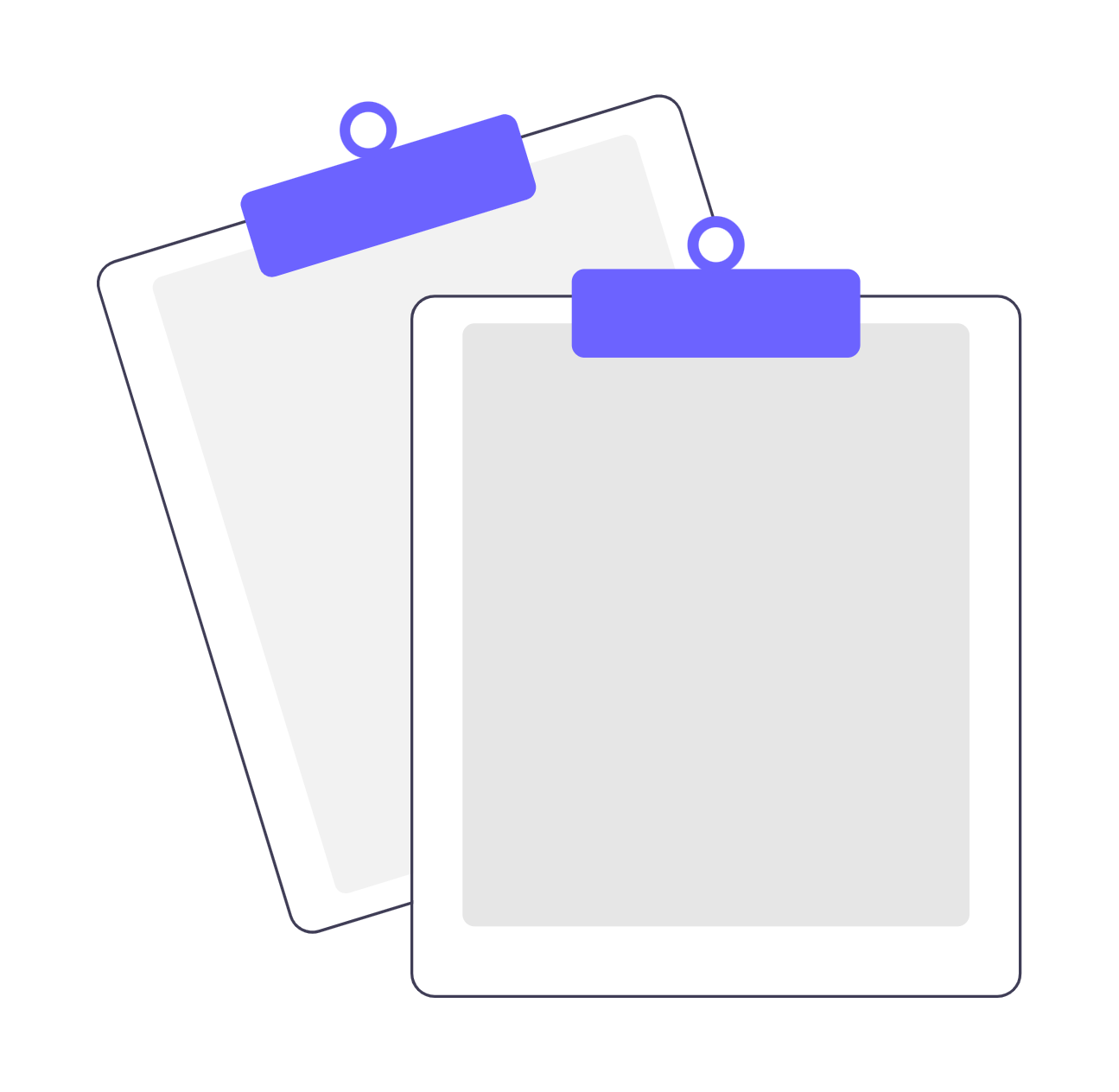在庫管理システムの選び方とは?業種別の比較ポイントと導入成功のコツを解説!
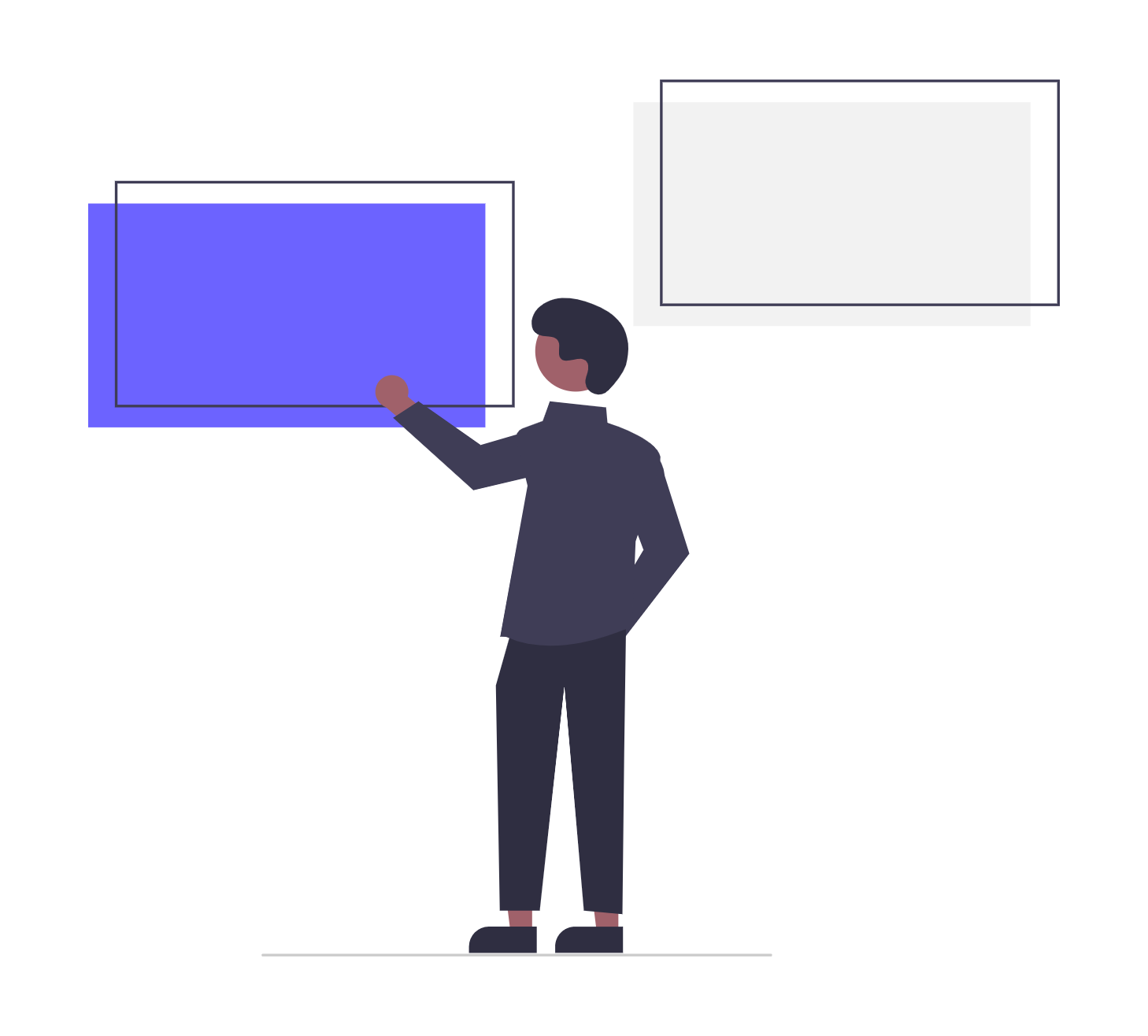
在庫管理システムの選び方とは?業種別の比較ポイントと導入成功のコツを解説!
「手作業やExcelでの管理に時間がかかり、ミスが多発している」「在庫数が合わず、過剰在庫や欠品で悩んでいる」——。これらは、多くの企業の在庫管理担当者が直面する典型的な課題です。もし一つでも心当たりがあれば、現在の管理方法が限界に達しているサインかもしれません。
実際に、商工中金が中小企業を対象に行った調査では、多くの企業がITシステム導入の最大の目的として「事務効率化・合理化」を挙げており、非効率な業務プロセスが経営課題となっている現状が浮き彫りになっています。
このような課題を解決する有効な一手こそが「在庫管理システム」の導入です。
この記事では、中小企業向けITシステム導入アドバイザーの視点から、自社に最適な在庫管理システムを選び、導入を成功させるための具体的なステップを網羅的に解説します。基本的な機能から業種別の選び方、導入後の落とし穴まで、体系的に学んでいきましょう。
1. なぜ今、在庫管理システムが必要なのか?
在庫管理システムは、単に在庫を数えるためのツールではありません。企業の収益性や競争力に直結する、戦略的な経営基盤です。まずは、システム導入がもたらす核心的なメリットと、従来の管理方法の限界を理解しましょう。
1-1. 在庫管理システムがもたらす4つの核心的メリット
システム導入は、ビジネスに以下の4つの大きな変革をもたらします。
- メリット1:在庫のリアルタイム可視化と適正化 システムを導入することで、いつ、どこに、何が、どれだけあるのかをリアルタイムで正確に把握できます。
これにより、勘や経験に頼った発注から脱却し、データに基づいた判断が可能になります。
過剰在庫による保管コストの増大や、欠品による販売機会の損失といったリスクを大幅に軽減できますが、これは単なるコスト削減に留まらず、キャッシュフローを改善し、新たな事業投資の原資を生み出すことに直結します。 - メリット2:業務効率の劇的な向上 バーコードやQRコードを読み取るハンディターミナルなどを活用することで、これまで手作業で行っていた入出庫や棚卸作業を自動化・高速化できます。
手入力や目視による確認作業がなくなるため、入力ミスや数え間違いといったヒューマンエラーを大幅に削減できるだけでなく、特に時間のかかる棚卸作業も劇的に短縮され、従業員の負担を大きく軽減します。 - メリット3:コスト削減への直接的貢献 業務効率化と在庫の適正化は、さまざまなコスト削減に直結します。適正在庫を維持することで、倉庫スペースの賃料や光熱費、品質劣化による廃棄ロスを圧縮できます。
また、棚卸や検品作業の時間が短縮されることで、残業代や人件費を削減し、創出されたリソースをより付加価値の高い業務に振り分けることが可能になります。 - メリット4:データ活用による経営判断の迅速化 システムに蓄積された入出庫データや在庫データは、経営判断に役立つ貴重な資産となります。
過去の販売実績データを分析することで、「どの商品がいつ、どれくらい売れるか」という需要予測の精度が高まり、より戦略的な仕入れ計画を立てられます。
また、在庫がどれくらいの期間で販売されたかを示す「在庫回転率」などの重要指標も可視化できます。
在庫回転率の改善は、投下した資本をいかに早く売上に変えているかを示す指標であり、企業の資金効率そのものを表します。
1-2. 紙やExcel管理では乗り越えられない「限界」とは
紙やExcelによる在庫管理は、手軽に始められる一方で、事業の成長とともに必ず限界が訪れます。
- 入力ミスや転記ミスの発生:手作業である以上、ヒューマンエラーをゼロにすることは困難です。
- 属人化のリスク:特定の担当者しか分からない「職人技」のような管理方法になりがちで、その担当者が不在の際に業務が滞るリスクがあります。
- リアルタイムでの情報共有が困難:複数の担当者が同時にファイルを更新できなかったり、最新情報がどれか分からなくなったりします。
- データ量の限界:扱う商品数やデータ量が増えると、ファイルの動作が重くなり、管理自体が非効率になります。
特に、アパレルや小売・卸売業のように、色・サイズ違いなど多品種(SKU)の商品を扱うビジネスでは、これらのアナログな手法では管理が追いつかなくなり、在庫差異や機会損失が頻発しやすくなります。
学習のポイント: 在庫管理システムの導入は、単なる業務効率化ツールではなく、企業の収益性と競争力を高めるための戦略的投資です。次のセクションでは、その戦略を実現するために、どのような種類のシステムがあるのかを体系的に見ていきましょう。
2. 【図解】在庫管理システムの種類を体系的に理解する
在庫管理システムと一言で言っても、その提供形態や機能範囲はさまざまです。導入を検討する担当者が最初に理解すべき、システムの分類方法を3つの視点から解説します。
2-1. 提供形態の違い:「クラウド型」と「オンプレミス型」
システムをどのように導入・利用するかという提供形態には、大きく分けて2つのタイプがあります。
- クラウド型:インターネット経由で提供されるサービスを利用する形態。自社でサーバーを持つ必要がなく、月額料金で利用できるのが一般的です。
- オンプレミス型:自社のサーバーにソフトウェアをインストールして利用する形態。自社内でシステムを構築・運用します。
両者の違いを以下の表にまとめます。近年、初期費用を抑えられ、導入もスピーディーなクラウド型が中小企業にとって主流になりつつあります。
|
特徴 |
クラウド型 |
オンプレミス型 |
|
初期費用 |
低い(または無料) |
高い |
|
導入スピード |
速い |
時間がかかる |
|
カスタマイズ性 |
制限あり |
高い |
|
セキュリティ |
ベンダーに依存 |
自社で構築 |
|
メンテナンス |
ベンダーが実施 |
自社で実施 |
2-2. 機能範囲の違い:「WMS」「OMS」「ERP」
在庫管理に関連するシステムは、その機能がカバーする範囲によって、主に3つのタイプに分けられます。これらのシステムの関係性を体に例えるなら、WMSは倉庫という『手足』の動きを司り、OMSは顧客からの注文を受ける『感覚器官』、そしてERPは会社全体の意思決定を行う『頭脳』に相当します。
- WMS (Warehouse Management System:倉庫管理システム) 倉庫内の「モノの動き」の管理に特化したシステムです。
入荷、検品、ピッキング(棚からの商品取り出し)、出荷、棚卸、ロケーション管理(商品の保管場所管理)など、倉庫内作業の正確性と効率性を高めることを目的としています。 - OMS (Order Management System:受注管理システム) ECサイトなど複数の販売チャネルからの「注文情報」を一元管理することに特化したシステムです。
受注処理、在庫情報の引き当て、出荷指示などを自動化し、顧客への迅速な対応を可能にします。在庫管理システムと連携することで、売り越しなどを防ぎます。 - ERP (Enterprise Resource Planning:統合基幹業務システム) 在庫管理だけでなく、販売、会計、生産、人事など、企業の基幹業務全体を統合管理するシステムです。
各部門のデータがリアルタイムで連携されるため、経営状況を俯瞰的に把握し、迅速な意思決定を支援します。
倉庫管理と在庫管理の違いについては、以下の記事でとても分かりやすく整理されています。
もしよろしければ、こちらも参考にしてみてください。
【5分で解決】在庫管理と倉庫管理の違いとは?業務内容からシステム選定方法まで徹底解説|在庫管理110番
2-3. 業態特化の違い:「汎用型」と「特化型」
あらゆる業種に対応できる「汎用型」のシステムに加え、特定の業界の商習慣や業務フローに合わせて専用設計された「業界特化型」「業態特化型」のシステムも存在します。
- ECサイト・通販特化型 複数のECモールやカートシステムとの在庫連携、受注から出荷までの一元管理機能が充実しています。
セット販売や予約販売など、EC特有の販売形態にも対応しています。 - 製造業特化型 原材料や部品、仕掛品(製造途中の製品)の管理、生産計画との連携機能が強みです。
ロット(生産単位)別の在庫追跡(トレーサビリティ)機能も重要です。 - アパレル・小売業特化型 色・サイズ別の在庫管理(SKU管理)や、店舗とECサイト間の在庫一元管理、POSレジとの連携機能が不可欠です。
委託在庫や催事販売など、業界特有の在庫形態にも対応します。 - 食品・医療業界特化型 賞味期限や使用期限の管理、ロット管理が厳格に行える機能が特徴です。
先入れ先出しを徹底するためのロケーション管理や、トレーサビリティ機能が重視されます。
学習のポイント: 自社のビジネスモデルや規模、将来の展望に合わせて、これらのタイプをどう組み合わせるか考えることが選定の第一歩です。次のセクションでは、具体的な選び方のステップを解説します。
3. 失敗しない!自社に最適な在庫管理システムの選び方【5つのステップ】
数あるシステムの中から自社に最適なものを選ぶには、体系的な比較検討プロセスが不可欠です。ここでは、システム選定を成功させるための5つのステップを解説します。
ステップ1:導入目的と解決したい課題を明確にする
システム選定における最初の、そして最も重要なステップは、『何のために導入するのか』という目的と、『何を解決したいのか』という課題を経営層から現場まで全員が合意できるレベルで言語化することです。これは、後のベンダー選定で用いるRFP(提案依頼書)の根幹にもなります。
以下の例のように、現状の課題を具体的に洗い出しましょう。
- 「棚卸作業に毎回2日間もかかり、他の業務が止まってしまう」
- 「ECサイトと実店舗の在庫が連携しておらず、売り越しが発生して顧客に迷惑をかけている」
- 「過剰在庫が多く、倉庫の保管コストが経営を圧迫している」
ちなみに、PRONIアイミツの調査によると、企業が在庫管理システムに求める機能の上位は「在庫情報の一元管理(94%)」「入出荷管理(89%)」「棚卸・ハンディターミナル機能(77%)」です。これらの基本的なニーズに加え、自社特有の課題は何かを整理することが、最適なシステム選びの出発点となります。
ステップ2:業種別の必須チェックポイントを確認する
自社の業種に合わせて、特に確認すべき機能をチェックリスト化しましょう。ここでは、アパレル、小売、卸売の3業種に焦点を当てて解説します。
- アパレル業のポイント
- 色・サイズ別在庫管理(SKU管理):Tシャツ1枚でも色とサイズで数十のSKUに分かれるため、この管理が甘いと人気商品の欠品や不人気商品の滞留に直結します。
- 委託在庫・予約在庫管理:百貨店などへの委託販売や、先行予約分の在庫を区別して管理できるか。
- 小売業のポイント
- POSレジ連携:店舗の売上データと在庫数がリアルタイムで連携されるか。
- 複数店舗間での在庫一元管理:全店舗の在庫状況を本部で一括把握し、店舗間の在庫移動を管理できるか。
- 卸売業のポイント
- ロット管理・賞味期限管理:製造ロットや賞味期限ごとに在庫を管理し、出荷期限の逆転を防げるか。
- 取引先ごとの価格設定:卸売業では、顧客との関係性や取引量によって販売価格が異なるのが常であり、この機能を欠くと手作業での価格調整という膨大な手間とミスが発生します。
- セット品管理:ギフトセットなど、複数の商品を組み合わせて販売する場合に対応できるか。
- 荷姿管理:ケース、ボール、バラなど、商品ごとの荷姿単位で在庫を管理できるか。
ステップ3:既存システムとの連携性を評価する
在庫管理システムは単体で機能する『島』ではなく、他の業務システムと連携する『ハブ』として機能させることで、その価値が飛躍的に高まります。連携方式には主に「API連携」と「CSV連携」の2つがあり、その違いを理解することが重要です。
|
連携方式 |
メリット |
デメリット・注意点 |
|
API連携 |
・リアルタイムで自動連携 |
・初期設定が必要 |
|
CSV連携 |
・多くのシステムが対応 |
・手動での作業が必要 |
リアルタイムでの正確なデータ共有を重視するなら、API連携に対応しているシステムが断然有利です。特に、以下のシステムとの連携は優先的に検討しましょう。
- 会計システム:仕入や売上のデータを自動で反映。
- 販売管理システム:受注情報と在庫データを連携。
- ECカート・モール:ECサイトの注文と在庫をリアルタイムで同期。
- POSシステム:実店舗の売上と在庫をリアルタイムで同期。
ステップ4:費用対効果を見極める
商工中金の調査でも、中小企業がシステム導入で直面する課題として「費用対効果」が上位に挙げられています。単に価格が安いだけでなく、導入によって得られる効果(コスト削減額、業務効率化の時間など)とのバランスを見極めることが重要です。
以下の費用項目を全て洗い出し、総額(TCO: Total Cost of Ownership)で判断しましょう。
- 初期費用
- 月額(または年額)費用
- ユーザー追加費用
- オプション機能の追加費用
- 導入サポート費用
多くのサービスが提供している無料トライアルやデモを積極的に活用し、実際の操作感や機能が価格に見合っているかを自分の目で確かめることを強く推奨します。
ステップ5:サポート体制と将来の拡張性を確認する
システムは導入して終わりではありません。導入後の運用をスムーズに定着させるためには、ベンダーの手厚いサポートが不可欠です。
- サポート内容の確認:導入時の設定支援、電話やメールでの問い合わせ対応、オンラインマニュアルの充実度などを確認しましょう。
- 将来の拡張性(スケーラビリティ):事業が成長し、取り扱い商品数や拠点、利用者数が増えた際に、システムが柔軟に対応できるかどうかも長期的な視点で重要な選定基準です。機能の追加やプランのアップグレードが容易かを確認しておきましょう。
学習のポイント: 最適なシステムとは、単に高機能なものではなく、自社の課題と成長戦略に寄り添ってくれるパートナーです。次のセクションでは、そのパートナーと共に導入を成功させるための具体的な方法を見ていきましょう。
システム比較・検討時に有効な F&G分析(フィット&ギャップ分析) については、下記の記事で詳しく解説しております。
ご参考までにご覧ください。
4. 導入を成功に導くための「落とし穴」回避術
優れたシステムを選んでも、導入プロセスでつまずいては意味がありません。ここでは、システム導入でよくある失敗パターンとその対策を解説します。
4-1. よくある導入失敗パターンとその対策
在庫管理システムの導入が失敗に終わる典型的なパターンと、それを回避するための具体的な対策を学びましょう。
- 失敗1:業務フローが未整理のまま導入してしまう。
- 対策:システム導入の契約を結ぶ前に、必ず現状の入庫から出庫までの業務フローを「見える化」しましょう。その上で、非効率な部分を洗い出し、新しいシステムに合わせて業務プロセスを標準化する「BPR(業務プロセス改革)」の視点を持つことが成功の鍵です。
- 失敗2:現場の意見を聞かずに導入を決めてしまう。
- 対策:システムを実際に使うのは現場の担当者です。選定段階の時点から現場のキーパーソンをプロジェクトに巻き込み、「何に困っているか」「どんな機能があれば楽になるか」をヒアリングしましょう。操作が直感的で、現場の負担を本当に軽減できるシステムを選ぶことが定着に繋がります。
- 失敗3:データ移行の計画が甘い。
- 対策:既存のExcelファイルや旧システムから新システムへデータを移す作業は、想像以上に複雑です。本番移行の前に、移行対象のデータ(商品マスタ、在庫数など)を事前に定義し、「何を、いつ、どのように」移行するのか綿密な計画を立てましょう。計画に基づいたリハーサルを徹底し、問題点を洗い出しておくことが不可欠です。
- 失敗4:導入後の教育・ルール作りを怠る。
- 対策:システム導入と同時に、運用ルールを明確に定める必要があります。例えば、「商品の保管場所(ロケーション)をどう管理するか」「返品処理はどう行うか」といったルールを決め、操作マニュアルを整備します。そして、全担当者向けに社内教育を実施し、全員が同じルールでシステムを使えるように徹底します。
システム導入時によくある「落とし穴」を回避するポイントについては、以下の記事で詳しく解説しております。
ご参考までに、ぜひご確認ください。
➡️ [こちらをクリック!]
- 対策:システム導入と同時に、運用ルールを明確に定める必要があります。例えば、「商品の保管場所(ロケーション)をどう管理するか」「返品処理はどう行うか」といったルールを決め、操作マニュアルを整備します。そして、全担当者向けに社内教育を実施し、全員が同じルールでシステムを使えるように徹底します。
4-2. システム移行方式の選択
現行の管理方法から新システムへ切り替える際には、いくつかの方式があります。主要な4つの移行方式の特徴を以下の表にまとめます。自社の業務への影響や許容できるリスクを考慮し、最適な方式を選択してください。
|
移行方式 |
概要 |
メリット |
デメリット |
|
一斉移行 |
特定のタイミングで一斉に新システムへ切り替える。 |
コストや手間を抑えやすい。 |
移行時に問題が発生した場合の影響が大きい。 |
|
順次移行 |
業務単位や機能単位で段階的に移行する。 |
問題発生時の影響を局所化できる。 |
移行期間が長くなり、コストや手間がかかる。 |
|
並行運用移行 |
旧システムと新システムを一定期間、並行して稼働させる。 |
トラブル時のリスクを最小限に抑えられる。 |
二重入力の手間がかかり、現場の負担が大きい。 |
|
パイロット移行 |
特定の部署や拠点だけで先行して導入し、検証後に全体展開する。 |
全社展開時のリスクを低減できる。 |
全体移行完了までに時間がかかる。 |
4-3. 導入成功企業に学ぶ実践のコツ
実際に在庫管理システムの導入に成功した企業には、いくつかの共通点があります。例えば、クラウド型WMS「クラウドトーマス」を導入した企業では、以下のような驚異的な改善効果が報告されています。
- 在庫差異率の改善:導入前22%(40万点中9万点の差異)だったものが、導入後には0.00001%(40万点中3点の差異)に劇的に改善。
- 生産性の向上:20名の人員で1日の最大出荷件数が800件だったのが、システム導入後は25名で4,000件に増加。
これらの成功事例に共通するポイントは、以下の3点です。
- 明確な目的意識:「なぜ導入するのか」という目的が経営層から現場まで社内で共有されている。
- 現場を巻き込んだ推進体制:選定から導入まで、現場担当者が主体的に関わっている。
- 導入支援サービスの活用:システムのプロであるベンダーのサポートを最大限に活用し、自社だけでは難しい設定や業務フロー構築を乗り越えている。
5. まとめ
この記事では、在庫管理システムの選定から導入成功までの道のりを、以下のステップで解説しました。
- 課題の明確化:なぜシステムが必要なのか、現状の課題を洗い出す。
- 種類の理解:クラウド/オンプレミス、WMS/OMS/ERPなど、自社に合うタイプを知る。
- 比較検討:業種別ポイント、連携性、費用対効果など、5つのステップで最適なシステムを絞り込む。
- 導入計画:失敗パターンを回避し、着実な導入計画を立てて実行する。
最適な在庫管理システムの導入は、単なる日々の業務効率化に留まりません。それは、企業のキャッシュフローを改善し、顧客満足度を高め、そして持続的な成長を支えるための経営基盤そのものを築くことに他なりません。
まずは自社の現状を正しく把握することから始め、この記事を羅針盤として、あなたの会社の最強のパートナーとなるシステムを見つけてください。
株式会社ディー・ティー・ピーでは、お客様がシステム導入を円滑に進められるよう、
無料でデモンストレーションからお見積りのご提示まで 対応しております。
ぜひお気軽にご相談ください。