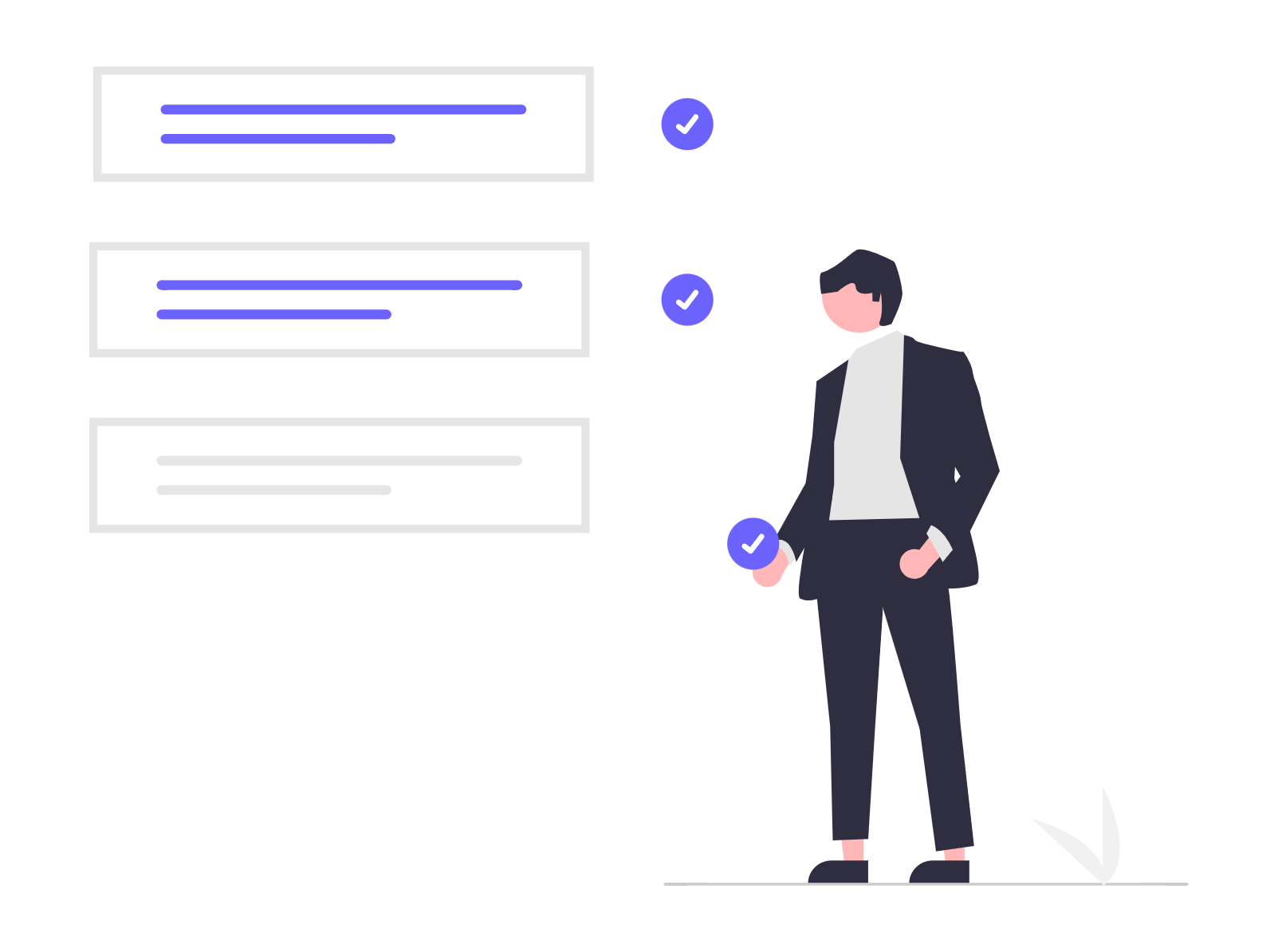フィットトゥスタンダードとは?メリット・デメリットや導入の注意点を解説

フィットトゥスタンダードとは?メリット・デメリットや導入の注意点を解説
フィットトゥスタンダード(FittoStandard)とは、システム導入におけるアプローチの一つで、自社の業務をパッケージ製品の標準機能に合わせていく考え方を指します。
この記事では、フィットトゥスタンダードの基本的な概念から、従来の導入手法との違い、具体的なメリットやデメリットについて詳しく解説します。
これからシステムの導入を検討している企業担当者の方は、自社にとって最適な方法を選択するための判断材料として、本記事の内容を参考にしてください。
フィットトゥスタンダードとは、システムに業務を合わせる考え方
フィットトゥスタンダードとは、ERPなどのシステムを導入する際に、カスタマイズを最小限に抑え、パッケージがもともと持っている標準機能に自社の業務プロセスを合わせていく考え方やアプローチを指します。
この手法では、システムが持つベストプラクティスをもとに業務フローを見直すことが前提となります。
フィットトゥスタンダードは、FittoStandardやFittostandardと表記されることもあり、変化の速い現代のビジネス環境において、迅速なシステム導入と継続的なアップデートを実現する上で重要な考え方です。
このアプローチは、システムの導入期間短縮、コスト削減、業務プロセスの標準化、そして常に最新の機能を利用できるといった多岐にわたるメリットを提供します。
なぜ今フィットトゥスタンダードが注目されているのか
フィットトゥスタンダードが注目される背景には、企業を取り巻く経営環境の急速な変化があります。
特に、クラウドサービスの普及により、常に最新の機能を利用できるSaaS型の基幹システムが増加しました。
これらのサービスは、標準機能の活用を前提としており、従来のカスタマイズ中心の手法ではアップデートに対応しにくいというIT面の課題があります。
また、多くの企業が直面する「2025年の崖」問題やDX推進の必要性から、複雑化した既存システムから脱却し、業務プロセス全体を標準化・効率化する必要性が高まっています。
フィットトゥスタンダードは、こうした変化に迅速かつ柔軟に対応するための有効なアプローチとして注目を集めているのです。
従来の手法「フィットアンドギャップ」との根本的な違い
フィットトゥスタンダードによるシステム導入は、企業に多くの効果をもたらします。
このアプローチを選択する際の重要なポイントは、コスト削減や導入期間の短縮といった直接的なメリットに加え、業務プロセスの標準化による組織全体の効率向上や、変化への対応力強化といった長期的な価値を理解することです。
ここでは、フィットトゥスタンダードがもたらす5つの主要なメリットについて解説します。
システムの導入期間を短縮しコストを削減できる
フィットトゥスタンダードの最大のメリットは、導入期間の短縮とコストの削減です。
従来のフィットアンドギャップでは、要件定義から設計、開発、テストといった工程で多大な時間と費用が発生していました。
しかし、フィットトゥスタンダードではシステムのカスタマイズを最小限に抑えるため、これらの工程を大幅に圧縮できます。
開発に伴う人件費や追加ライセンス費用などのコストが削減されるだけでなく、プロジェクト全体の期間が短くなることで、管理負荷も軽減されます。
これにより、企業はより迅速に新しいシステムを稼働させ、投資効果を早期に得ることが可能となります。
常に最新のシステム機能を使えるようになる
フィットトゥスタンダードは、特にクラウドベースのSaaS製品と相性が良いアプローチです。
SaaSでは、ベンダーが定期的に法改正対応や機能改善、セキュリティ強化のためのアップデートを行います。
システムをカスタマイズしていると、このアップデートが適用できなくなったり、適用するために追加の改修費用が発生したりする場合があります。
しかし、標準機能をそのまま活用していれば、ベンダーが提供する最新の機能を自動的に利用できるようになります。
これにより、自社で大きな労力をかけることなく、常に最適化された状態で製品を使い続けることができ、システムの価値を最大限に活用できます。
業務プロセスが標準化され属人化を防げる
システムの標準機能に業務フローを合わせる過程で、社内の業務プロセスが標準化されます。
多くのERPパッケージには、世界中の優良企業の業務プロセス(ベストプラクティス)が反映されており、これを取り入れることで自社の業務をより洗練されたものへと改善できます。
プロセスが標準化されると、特定の担当者しか業務内容を把握していないといった属人化の状態が解消されます。
これにより、担当者の異動や退職があっても業務が滞るリスクが低減し、組織全体の業務効率化が実現します。
業務の透明性が高まるという点も大きな利点です。
グローバル基準の業務プロセスを構築しやすい
多くの主要なERPパッケージは、グローバルでの利用を前提に設計されており、各国の法制度や商習慣に対応した機能が標準で備わっています。
フィットトゥスタンダードのアプローチを採用することで、これらのグローバル基準の業務プロセスを自社に容易に取り入れることが可能です。
これは、将来的に海外拠点への事業展開を計画している企業にとって、大きなアドバンテージとなります。
各拠点で個別にシステムを構築するのではなく、統一された業務基盤を迅速に展開できるため、ガバナンスの強化やグローバルでのデータ活用がスムーズに進みます。
ビジネス環境の急な変化にも柔軟に対応可能
現代のビジネス環境は、市場のニーズ、法規制、競合の動向などが目まぐるしく変化します。
従来のカスタマイズを多用したシステムは、構造が複雑化し、少しの変更にも多大な時間とコストがかかる硬直的な状態に陥りがちでした。
フィットトゥスタンダードで導入されたシステムは、標準機能を中心に構成されているため構造がシンプルです。
そのため、ビジネスの変化に応じて新しい機能を追加したり、設定を変更したりする際も、迅速かつ柔軟な対応が可能です。
この俊敏性が、企業の競争力を維持・向上させる上で非常に重要な要素となります。
フィットトゥスタンダードでシステムを導入する5つのメリット
フィットトゥスタンダードによるシステム導入は、企業に多くの効果をもたらします。
このアプローチを選択する際の重要なポイントは、コスト削減や導入期間の短縮といった直接的なメリットに加え、業務プロセスの標準化による組織全体の効率向上や、変化への対応力強化といった長期的な価値を理解することです。
ここでは、フィットトゥスタンダードがもたらす5つの主要なメリットについて解説します。
システムの導入期間を短縮しコストを削減できる
フィットトゥスタンダードの最大のメリットは、導入期間の短縮とコストの削減です。
従来のフィットアンドギャップでは、要件定義から設計、開発、テストといった工程で多大な時間と費用が発生していました。
しかし、フィットトゥスタンダードではシステムのカスタマイズを最小限に抑えるため、これらの工程を大幅に圧縮できます。
開発に伴う人件費や追加ライセンス費用などのコストが削減されるだけでなく、プロジェクト全体の期間が短くなることで、管理負荷も軽減されます。
これにより、企業はより迅速に新しいシステムを稼働させ、投資効果を早期に得ることが可能となります。
常に最新のシステム機能を使えるようになる
フィットトゥスタンダードは、特にクラウドベースのSaaS製品と相性が良いアプローチです。
SaaSでは、ベンダーが定期的に法改正対応や機能改善、セキュリティ強化のためのアップデートを行います。
システムをカスタマイズしていると、このアップデートが適用できなくなったり、適用するために追加の改修費用が発生したりする場合があります。
しかし、標準機能をそのまま活用していれば、ベンダーが提供する最新の機能を自動的に利用できるようになります。
これにより、自社で大きな労力をかけることなく、常に最適化された状態で製品を使い続けることができ、システムの価値を最大限に活用できます。
業務プロセスが標準化され属人化を防げる
システムの標準機能に業務フローを合わせる過程で、社内の業務プロセスが標準化されます。
多くのERPパッケージには、世界中の優良企業の業務プロセス(ベストプラクティス)が反映されており、これを取り入れることで自社の業務をより洗練されたものへと改善できます。
プロセスが標準化されると、特定の担当者しか業務内容を把握していないといった属人化の状態が解消されます。
これにより、担当者の異動や退職があっても業務が滞るリスクが低減し、組織全体の業務効率化が実現します。
業務の透明性が高まるという点も大きな利点です。
グローバル基準の業務プロセスを構築しやすい
多くの主要なERPパッケージは、グローバルでの利用を前提に設計されており、各国の法制度や商習慣に対応した機能が標準で備わっています。
フィットトゥスタンダードのアプローチを採用することで、これらのグローバル基準の業務プロセスを自社に容易に取り入れることが可能です。
これは、将来的に海外拠点への事業展開を計画している企業にとって、大きなアドバンテージとなります。
各拠点で個別にシステムを構築するのではなく、統一された業務基盤を迅速に展開できるため、ガバナンスの強化やグローバルでのデータ活用がスムーズに進みます。
ビジネス環境の急な変化にも柔軟に対応可能
現代のビジネス環境は、市場のニーズ、法規制、競合の動向などが目まぐるしく変化します。
従来のカスタマイズを多用したシステムは、構造が複雑化し、少しの変更にも多大な時間とコストがかかる硬直的な状態に陥りがちでした。
フィットトゥスタンダードで導入されたシステムは、標準機能を中心に構成されているため構造がシンプルです。
そのため、ビジネスの変化に応じて新しい機能を追加したり、設定を変更したりする際も、迅速かつ柔軟な対応が可能です。
この俊敏性が、企業の競争力を維持・向上させる上で非常に重要な要素となります。
フィットトゥスタンダードのデメリットと注意すべき点
フィットトゥスタンダードは多くのメリットを持つ一方で、導入にあたって考慮すべきデメリットや課題も存在します。
特に、既存の業務プロセスを大幅に変更する必要があるため、現場の従業員からの反発を招く可能性があります。
導入を成功させるためには、これらの注意点を事前に理解し、適切な対策を講じることが重要です。
ここでは、フィットトゥスタンダードを進める上で直面しがちな課題について解説します。
既存の業務フローを大幅に変更する必要がある
フィットトゥスタンダードを導入する上で最も大きな障壁となり得るのは、既存の業務フローを大幅に変更する必要がある点です。
特に、長年にわたって独自の業務プロセスを構築し、それが企業の競争力の源泉となっている場合、システムに合わせて業務を刷新することへの抵抗は大きくなります。
現場の従業員にとっては、慣れ親しんだやり方を変えることは大きな負担となり、一時的に生産性が低下する可能性も否定できません。
導入前には、なぜ業務フローの変更が必要なのか、それによってどのようなメリットが生まれるのかを丁寧に説明し、現場の理解を得るプロセスが不可欠です。
従業員が新しいシステムに慣れるまで時間がかかる
新しいシステムの導入は、必然的に従業員の学習コストを伴います。
フィットトゥスタンダードでは、システムの変更と同時に業務プロセスの変更も発生するため、従業員が新しいやり方に慣れるまでには相応の時間が必要です。
操作方法を覚えるだけでなく、なぜそのプロセスになったのかという背景まで理解しなければ、効果的な運用は望めません。
この課題を乗り越えるためには、導入プロジェクトの初期段階から社内への十分な情報共有を行い、マニュアルの整備や段階的なトレーニングプログラムを計画的に実施することが求められます。
定着を急ぐあまり、現場の混乱を招かないよう配慮が必要です。
複数のシステムを組み合わせると運用が複雑化する恐れ
導入するシステムの標準機能だけでは、自社の業務要件をすべて満たせない場合があります。
その際、不足する機能を補うために、他のSaaSや外部ツールを組み合わせて利用することが考えられます。
このアプローチは有効な一方で、複数のシステムを連携させることにより、運用が複雑化するリスクをはらんでいます。
特に、システム間のデータ連携がスムーズに行えない場合、手動でのデータ入力や転記作業が発生し、かえって非効率になる可能性があります。
システム全体のアーキテクチャを事前に設計し、データの一貫性や連携方法を十分に検討した上で、適切な組み合わせを選択する必要があります。
フィットトゥスタンダードを成功に導くための導入ステップ
フィットトゥスタンダードのアプローチでシステム導入を成功させるためには、計画的かつ段階的な方法でプロジェクトを推進することが不可欠です。
単にシステムを導入するだけでなく、業務改革を伴う大きなプロジェクトであることを全社で認識する必要があります。
ここでは、フィットトゥスタンダードを成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。
この流れに沿って進めることで、導入の目的を達成しやすくなります。
ステップ1:現状の業務プロセスを洗い出し課題を明確にする
最初のステップは、自社の現状を正確に把握することから始まります。
特定の部門だけでなく、関連する全部門の業務プロセスを詳細に洗い出し、フローチャートなどを用いて可視化します。
これにより、誰が、いつ、どのような作業を行っているのかという業務の全体像が明確になります。
プロセスを可視化する過程で、非効率な作業、部門間の連携不足、属人化している業務といった潜在的な課題が浮き彫りになります。
この客観的な現状分析が、後のシステム評価や業務プロセスの再設計において、的確な判断を下すための重要な土台となります。
ステップ2:システムの標準機能で業務が遂行できるか評価する
次に、導入を検討しているERPなどのシステムが持つ標準機能と、ステップ1で洗い出した自社の業務プロセスを照らし合わせ、適合性を評価します。
この段階では、どの業務がシステムの標準機能でそのまま代替できるか、どの業務が現行のやり方から変更が必要になるかを具体的に確認します。
すべての業務を一つのソリューションでカバーできない場合は、他のツールとの連携や代替案も検討します。
この評価を通じて、導入するシステムが自社の業務とどれくらいの相性を持つのかを判断し、適切な製品を最終的に選定します。
机上の評価だけでなく、実際のデモやトライアルを活用することも有効です。
ステップ3:システムに合わせて業務プロセスを再設計する
システム選定後、その標準機能に合わせて新しい業務プロセスを具体的に再設計します。
ここでは、単にシステムの機能に業務を当てはめるだけでなく、ステップ1で明確になった課題を解決し、より効率的なフローを構築するという改善の視点が重要です。
例えば、これまで紙やExcelで行っていた申請・承認フローを、システムのワークフロー機能に置き換えるといった具体的な設計を行います。
この新しい業務プロセスは、関係部署の担当者も交えて検討し、現場の実態に即した、実用的なものであることが求められます。
再設計したプロセスは、マニュアルとして文書化し、全社で共有します。
ステップ4:従業員へのトレーニングを実施し定着を図る
最後のステップは、新しいシステムと業務プロセスを社内に定着させるための活動です。
まず、再設計された業務プロセスとシステムの操作方法について、全従業員を対象としたトレーニングを実施します。
役割や部署に応じた研修プログラムを用意し、実践的な演習を取り入れることで理解を深めます。
システム導入後も、問い合わせに対応するためのヘルプデスクを設置したり、活用方法に関する勉強会を定期的に開催したりするなど、継続的なフォローアップが欠かせません。
従業員が新しいやり方にスムーズに移行できるよう、丁寧なサポートを通じて定着を促します。
まとめ
フィットトゥスタンダードは、システムの標準機能に業務を合わせることで、導入期間の短縮、コスト削減、業務標準化といった多くのメリットをもたらすアプローチです。
この考え方は、特にクラウドサービスが主流となった現代において、変化の速いビジネス環境に企業が適応していくための有効な手法といえます。
従来のフィットアンドギャップとは異なり、業務プロセスの大幅な見直しが求められるため、導入には慎重な計画と社内の合意形成が不可欠です。
本記事で解説したメリット・デメリットや導入ステップを理解し、自社のシステム戦略を検討する上でフィットという選択肢を評価することが、今後の継続的な成長の鍵となります。
本記事でも軽く触れた フィット&ギャップ分析(F&G分析) について、
より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
システム導入における「適合」と「乖離」を見極めるための具体的な進め方を解説しています。